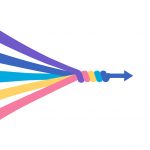ユニセフとはどのような活動をしているか
ユニセフの沿革をおさらい
ユニセフとは国際連合児童基金、United Nations Children’s Fundの略称で、1946年の12月に設立されました。
国際連合総会の補助機関で本部はアメリカのニューヨークに置かれていて、1965年にノーベル平和賞を受賞しました。
シンボルマークは平和のしるしであるオリーブの葉に囲まれた地球で、子供が高く抱き上げられている図です。
主な活動は戦後の緊急援助が必要な子供を対象とした援助活動で、日本でも1946年から1964年にわたって脱脂粉乳や医薬品などの援助を受けていました。
開発途上国や戦争、内戦で被害を受けている多くの子供達へ、保健、栄養、水と衛生、教育、エイズ問題、保護、緊急支援などの活動を実施し、子供の生存のための基本的な社会サービスの支援と提言を各政府にむけて行っています。
児童の権利に関する条約の普及活動にも努めており、以前はひたすら物資の援助をしていましたが、本人たちの自立なくしては状況は変わらないとして親への啓もう活動にも取り組んでいます。
いくら物資を与えてもそれに甘えて自分達で抜け出そうとしなければ、結局支援していることにならないからでしょう。
子供の権利条約が定めている権利とは、生きる権利、育つ権利、守られる権利、参加する権利の4つです。
生きる権利では防げる病気や治療が出来る怪我などで命が奪われないことであり、すべての子供達が病気や怪我の時にきちんとした治療を受けられる権利です。
育つ権利について
育つ権利では教育を受けてゆっくり休んだり楽しく遊んだりすることが出来ることとであり、子供が自分自身で考えたり信じたりすることの自由が守られ、自分らしく育つことが出来る権利です。
守られる権利では、あらゆる種類の虐待や搾取などから子供が守られる権利をさします。
障害を持つ子供や少数民族の子供などは特に守られなければなりません。
最後の参加する権利は、自由に意見を表したり集まってグループを作ったり、たくさんの自由な活動を行ったりできる権利です。
世界の様々な国では日本では当たり前と思われているこれらのことが、簡単に出来ない、させてもらえない子供達が現在でも多く存在しているのです。
例えばカンボジアでは障害に対する社会的な理解が不足していて、障害がある人たちへの支援制度は不備が多いのが現状です。
教育や医療などの基本的な社会サービスを受けにくい状況にあるので、募金をすることで専用の学習教材の開発などが促進できるのです。
各国の協会では小学校などに出前授業にいくこともあり、絶えず啓蒙活動を続けていくことで、先進国の豊な子供達にもこのようなことを知ってもらえるようになるでしょう。
ユニセフの本部では執行理事会があり、36か国の政府代表で構成されています。
委員は国連の経済社会理事会で選出され、任期は3年間、基本方針の決定や援助の計画をたてること、予算の審議及び承認が主な業務内容です。
ユニセフでは世界で7つの地域に存在する地域事務所、155の国と地域に存在する現地事務所、そして本体とは協力協定を結んでいるけれども全く別の民間団体NGOとして各国に設置されている国内委員会があります。
日本ユニセフ協会について
日本では日本ユニセフ協会がそれにあたります。
日本国内で本部のために募金や寄付を宣伝する唯一の国内委員会であり、本部に認可された団体です。
よくユニセフに募金や寄付をするとその全部が支援のために使われるわけではないから嫌だ、とか、寄付金の使途が不明瞭であるという意見がありますが、それには理由があります。
例えば他の支援事業のように別に営利目的の行動(副業行為)をしていればそこから運営費を支払うことが出来ますが、ユニセフでは募金や寄付以外から事業の活動費を捻出できません。
そのために集めた資金から活動費を消費するので、前提として募金の100パーセントが支援される側に届くわけではないと理解が必要です。
支援先は、主に5歳未満の子供の死亡率やその国の経済状況と子供の人口の3つを基準にして決められますが、指定募金という方法もあります。
指定募金とは支援先を指定して支援する方法で、送られた募金は指定された国の事業で使われます。
寄付をするのは良いが、自分が用意したお金は本当に困っている人に使われたいのに宣伝費や活動費に使われるのは嫌だから、直接ニューヨークの本部に寄付したいのだがその方法はないだろうか、といった質問が、インターネット上では度々出てきます。
回答としては、それは出来ません。
本部では直接の寄付を受け付けてくれませんので、あくまでも各国の協力関係にある協会での受付になります。
募金や寄付の仕方はいろいろあります。
クレジットカードを使っての募金、郵便局や銀行からの引き落とし、電子マネーの利用、コンビニエンスストアでの募金箱の利用、電話での寄付、携帯電話料金と一緒に引き落としされるなどです。
ちなみに寄付は税金控除の対象となりますので約40パーセントとが所得税額から控除されます。
最終更新日 2025年7月8日 by mdchiefs